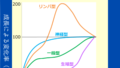足底腱膜炎のメカニズムと靴・インソールでの対処法
足底腱膜炎の発生メカニズム

解剖学的背景
足底腱膜は、踵骨(かかとの骨)から始まり、足指の基部(中足骨頭)に向かって扇状に広がる結合組織です。これにより、足の縦アーチ(内側縦足弓)を支えるとともに、歩行時のエネルギー保存と衝撃吸収に関与します。足底腱膜が過剰に伸長されると、その付着部である踵骨隆起に過度のストレスが加わり、小さな断裂が生じることがあります。この反復的な損傷が炎症を誘発し、痛みとして現れます。
生物力学的要因
足底腱膜炎の発症には以下の生物力学的要因が関与します:
- 足のアーチの異常:扁平足では足底腱膜が過度に伸ばされ、ハイアーチでは衝撃吸収が不十分になるため、どちらもリスク因子となります。
- 筋腱の硬さ ;下腿三頭筋(腓腹筋とヒラメ筋)が硬直していると、足首の背屈制限が生じ、足底腱膜に過度のテンションがかかります。
- 歩行やランニングの不適切なフォーム: 特に踵からの衝撃吸収が不十分な場合、足底腱膜へのストレスが増大します。
症状の特徴
- 疼痛: 主に踵骨隆起付近に鋭い痛みを感じ、特に起床後の一歩目で顕著。
- 硬直感: 朝や長時間の休息後に足裏が硬直し、痛みが出やすい。
- 慢性化: 症状が進行すると、歩行や日常生活にも支障をきたします。
足底腱膜炎からの悪化がこわい。踵骨棘のメカニズム↓
靴とインソールによる専門的な対処法

靴の選定
足底腱膜炎の管理には、足底にかかる負荷を分散させる靴が重要です。
- ヒールカウンターの強化:踵部分をしっかりサポートすることで、骨格が安定し、足底腱膜へのストレスを軽減します。
- 適切なミッドソールの硬さ:柔らかすぎないミッドソールは足底腱膜を支え、足の安定性を向上させます。
- 緩い靴は避ける:脱ぎ履きしやすい靴は、靴の中で必要以上に足が動いてしまい、足趾を緊張させる要因になります。その結果、足底腱膜にストレスがかかりやすくなります。
- ローリングソール: 歩行時の足の屈曲を助け、足底腱膜への負担を軽減します。
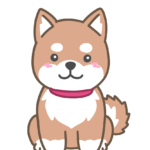
広い、緩い、脱ぎ履きしやすい靴は、足底筋膜炎を悪化させます。
インソールの使用
インソールは、足底腱膜への負荷を効率的に分散するための効果的なツールです。
- 既成インソール :一般市販されているものでも、アーチサポートとクッション性が高い製品は有用です。
- カスタムメイドインソール: 足型に基づいて作成されるオーダーメイドのインソールは、最大の効果を発揮します。特に内側縦アーチを適切に支える設計が望まれます。
- ヒールリフト(踵上げ): 踵部分を少し高くすることで下腿三頭筋をゆるめ、足底腱膜の緊張を緩和します。ただし上げすぎは、足趾を緊張させる要因になるので、注意が必要です。
併用療法と予防

靴やインソールに加えて、以下の治療法や予防策を組み合わせるとより効果的です:
- ストレッチと筋力強化: 腓腹筋・ヒラメ筋や足底筋群を柔軟に保ち、筋力を向上させるエクササイズ。
- 理学療法: 超音波療法や低周波治療による疼痛軽減。
- 体重管理 :足底への負担を減少させるための健康的な体重維持。
- テーピング: 動きを制限し、負荷をコントロールするためのキネシオロジーテープや固定テープ。
足底腱膜炎の治療は、原因に基づいた多角的なアプローチが必要です。専門的な視点で靴やインソールを選び、適切なケアを継続することで症状を和らげ、再発を予防することが可能です。痛みが続く場合は、整形外科や専門的な靴屋さんに相談することをお勧めします。
靴屋さん的見解というささいな話
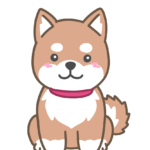
ここからは独自の見解になりますので、お気軽に読んでね。
足裏の痛みのほとんどが、足底腱膜炎によるものが多いと思われます。特に多く拝見するのが、指定靴(安全靴など)や、脱ぎ履きが多くある方、革靴で多く歩く方です。どうしても靴に足を守る機能が少なく、足に負担がかかりやすい傾向にあります。
そのような靴に指定がある場合はインソールで調整する場合が多いのですが、まずはお持ちの靴のサイズに問題がないか、靴の機能は最低限あるか…など確認します。またお客様とお話し、靴の変更等が可能かどうかも確認していきます。なんとなくの印象ですが、インソール1枚で色々な負担軽減ができると、大きな期待をもたれている方が多くいらっしゃるな…と感じることが少なくありません。
インソールは無いよりはマシにはできますが、靴を変えられるのならば、その方が大きな効果が期待できます。ネットで調べるとインソール…すごそうな機能がたくさん搭載されているように感じますからね。
まずは靴を見直しましょう!!

ということで、今回は足底腱膜炎について記事にさせていただきました。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。
足と靴の知識を深めることは、日々の生活に直結する重要な要素です。皆さまに役立つ情報をお届けできるよう、今後も現場での経験と、専門的な知識をもとに記事を投稿してまいります。
引き続き、足と靴の健康を守るための情報を発信していきますので、ぜひチェックしてください。
good luck