
糖尿病は血糖値の異常を引き起こし、全身にさまざまな影響を及ぼす疾患です。特に足部への影響は大きく、神経障害や血行不良を伴うことで、傷が治りにくく、重症化すると足の切断を余儀なくされるケースもあります。本記事では、糖尿病と足の関係を医学的視点から解説し、靴やインソールによる対応策について詳述します。
糖尿病と足の問題
糖尿病が足に影響を与える主要な要因

末梢神経障害(ニューロパシー)
糖尿病によって神経障害が進行すると、足の感覚が鈍くなり、痛みや温度変化に気づきにくくなります。これにより、小さな傷や圧迫による皮膚の損傷が悪化しても気付かず、感染症や潰瘍に発展する可能性があります。特に足趾(足指)の先のほうが、感覚が鈍くなりやすいので、感覚テストなどを行い、現在の状況を把握することが大切になります。
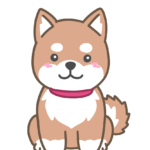
感覚がないって、とても怖いことなんだ…。
血行障害(末梢動脈疾
高血糖の影響で血管が硬化し、末梢の血流が低下します。血行不良が進むと、傷の治癒が遅れ、壊疽のリスクが高まります。皮膚の色が少し紫がかった色になる傾向にあります。
足の変形と圧力分布の異常
神経障害により足の筋肉が萎縮し、アーチの崩れや足趾の変形(ハンマートゥなど)が生じます。これにより特定部位への圧力が集中し、皮膚の損傷や潰瘍形成の原因になります。
靴とインソールによる足の保護

糖尿病患者の足を守るためには、適切な靴とインソールの選択が重要です。
糖尿病患者向けの靴の特徴
糖尿病患者向けの靴は、足の保護と圧力の分散を目的としています。選択する際のポイントは以下の通りです。
- つま先の広いデザイン:足趾の圧迫を避け、摩擦や傷のリスクを軽減。
- クッション性の高いソール:衝撃吸収性に優れ、足底への圧力を緩和。
- シームレス構造:靴内部の縫い目が少なく、擦れによる皮膚の損傷を防ぐ。
- 通気性の良い素材:湿気を逃がし、感染症リスクを低減。
また、靴を履く際には靴紐やベルトでしっかりと足を固定し、靴の中で足がずれないよう調整することが重要です。
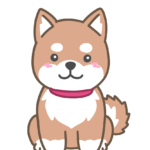
脱ぎ履きしやすい、ゆるい靴はトラブル悪化につながりやすいです。
インソールの役割と選び方
適切なインソールを使用することで、足部の圧力を分散し、神経障害や血行障害による負担を軽減できます。
- 足圧分散型インソール:特定部位への負担を減らし、皮膚潰瘍の予防に寄与。
- アーチサポート付きインソール:足の形を適切に保ち、変形を防ぐ。
- クッション性の高い素材:衝撃を吸収し、歩行時の負担を軽減。
糖尿病患者には、医療用インソール(オーダーメイド)の使用が推奨されます。個々の足の状態に応じた設計が可能であり、より効果的な足の保護が期待できます。
糖尿病患者が日常で気を付けること

靴とインソールの選択以外にも、日々のケアが糖尿病性足病変の予防に不可欠です。
足の定期チェック
毎日、足に傷や変色がないかをチェックし、異常があればすぐに医師に相談する習慣をつけましょう。特に足の裏や足趾の間は見落としやすいため、入念な確認が必要です。
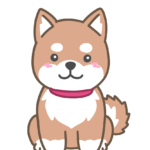
こまめな足のチェックを欠かさず行いましょう。
定期的な運動
糖尿病の患者様は医師から「ウォーキングをしてください」など運動を進められることが多いです。これは、血糖値のコントロールや心血管疾患のリスク低下など、様々なメリットがあるからです。しかしその時に履く靴の選択を間違えると、大きな足のトラブルに繋がりかねません。心配な場合は、専門の靴屋さん等で相談することも選択肢のひとつと考えます。
保湿と清潔保持
乾燥による皮膚の亀裂を防ぐため、適度な保湿を心掛けます。ただし、足趾の間には過度にクリームを塗らないようにし、湿気がこもらないよう注意が必要です。
適切な靴下の選択
糖尿病患者向けのシームレスソックスや圧迫の少ないソックスを選ぶことで、足の負担を軽減できます。吸湿速乾性の高い素材も、足の清潔維持に役立ちます。
靴を履くときの注意
靴を履く前に、必ず靴の中に異物などが入っていないか注意すること。靴の中の異物に気づかず、履いて帰ってきたら、足が血だらけになっていたなんて話も聞きます。
靴屋さん的見解というささいな話
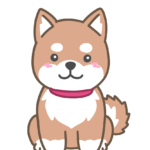
ここからは個人的な意見になります。お気軽に読んでね。
糖尿病は1型と2型があり、多くの人は2型の生活習慣病が原因の方が多くいらっしゃいます。個人的な意見になりますが、いわゆる「糖尿病気質」といわれる、あまり人の言うことを聞いてくれない傾向にあります。靴の履き方は、糖尿病足にとって、とても大切になりますが、なかなか聞き入れてくれない場面も多々あります。(そんな方ばかりではないですが…)
糖尿病で来店された方には、足趾の感覚テストをおこなうのですが、足趾の先にほとんど感覚がないのを知り、かなりビックリりされる方も少なくありません。初期症状がほとんどなく、気づかないうちに進行し、様々な合併症を引き起こすため、「陰から忍び寄る病」とも呼ばれます。
また、足趾切断までいって、はじめて靴選びをされる方も拝見し、もっと早く靴選びをはじめていれば…と思うことも多々あります。少し強い言い方になりますが、あかの他人にどこまで、話をもっていけばいいか…と思い悩むことも少なくありません…。未来がみえるわけではないですが、経験上、このままだと、おそらく悪化するだろうな…と予想することはできるので、それをどう伝えるか苦悩します。
少し極端な話になってしまいましたが、現場ではそんな思いもしながら靴選びのお手伝いをしてたりもします。今回取り上げた糖尿病は、ほんとうに怖い病気です。「陰から忍び寄る病」とはよく言ったものです。少しでも糖尿病足の重症化が防げるお手伝いができれば…と。

というこで、今回は糖尿病と足と靴の関係性について記事にさせていただきました。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。
足と靴の知識を深めることは、日々の生活に直結する重要な要素です。皆さまに役立つ情報をお届けできるよう、今後も現場での経験と、専門的な知識をもとに記事を投稿してまいります。
引き続き、足と靴の健康を守るための情報を発信していきますので、ぜひチェックしてください。
good luck




