
はだし保育は、日本の保育施設で広く導入されている教育方針の一つです。子どもの健康的な発達を促す目的で行われるこの取り組みは、特に足の発育や運動能力の向上に寄与するとされています。しかし、近年ではその効果に対する科学的な検証が進み、メリットだけでなく問題点も指摘されるようになっています。本記事では、足と靴の観点からはだし保育の現状と問題点を専門的に考察します。
はだし保育は、足にとって本当に良いのだろうか?
はだし保育の目的とメリット
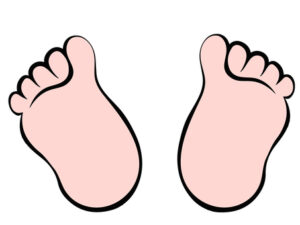
まず、はだし保育のメリット考察すると、以下の通りです。
- 足の筋力発達の促進
はだしで歩くことで足底筋群が活性化し、土踏まずの形成を助けるとされています。特に幼児期は足のアーチが未発達であり、適切な運動を与えることで健全な足の生育を育むことが期待されます。 - バランス感覚と運動能力の向上
靴を履かないことで足裏の感覚が鋭敏になり、地面の質感を直接感じることができます。これにより、バランス感覚が向上し、姿勢の安定性、転倒リスクの低減につながると考えられています。 - 血行促進と健康増進
足裏には多くの神経が集まっており、適度な刺激を受けることで血行が促進されます。これにより、冷え性の予防や免疫力の向上が期待されます。
はだし保育の問題点

一方で、はだし保育にはいくつかの問題点も指摘されています。メリットに対する問題点を考察していきます。
- 土踏まずの形成は2歳半ごろから
土踏まずの形成が2歳半ごろからはじまると考えたときに、それよりも年齢が小さい子に対しては、土踏まずの形成は期待できません。歩行もまだ安定していないので、転倒リスクなど注意が必要です。 - 地面の考慮
確かに裸足のほうが足裏は敏感になり、感覚の向上にプラスになると考えます。しかし土や砂、芝生のようなやわからい地面を裸足で歩くことは、足にとってとてもプラスになると思いますが、園内の床や、硬い地面に対しての裸足での運動は、衝撃吸収が十分でなく、足を痛める可能性が考えられます。地面の考慮はとても大事な要素と考えます。 - 季節の寒暖差
裸足での適切な刺激により、血行促進が期待されますが、夏の暑い日、冬の寒い日の足の保護は考慮にいれなくてはなりません。幼児の足は柔らかく、デリケートなため、注意必要です。 - 幼児の足の個性についての考慮
裸足がすべての幼児にプラスになるとは限りません。外反足や関節弛緩など、不安定要素の強い子に関しては、その症状を助長する可能性があります。その子に合った、適切な地面の選定や、活動時間の調整が必要になります。 - 靴への適応問題
はだしに慣れすぎると、靴を履いた際に違和感を覚える子どもが増えることがあります。また、はだし保育をとりいれている園は、基本的に靴を履くときも裸足の場合は多いです。靴は靴下を履いて履く設計になっていますので、適切ではありません。はだし保育は取り上げているが、靴に関しての教育は行われていないのが現状です。
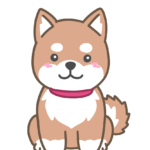
なんでもかんでも裸足が良いという考え方は危険ですね。
足と靴の観点からの改善策

はだし保育のメリットを活かしつつ、問題点を軽減するためには、以下のような対策が考えられます。
- 適切な環境整備
園庭や屋内の床材を工夫し、足に優しい素材を使用することで、裸足の効果を最大限に発揮できます。例えば、柔らかい芝生やクッション性のある床材を導入することで、足への負担を減らすことが可能です。 - 個々の足の状態をチェック
幼児の足は発育状態で、様々なバランスの子が存在します。裸足でも問題ない子、少し不安定になる子、裸足だと問題がある子、その確認を教育者が行い、適切な時間と場所で、はだし保育をおこなっていくことが重要と考えます。教育者に足と靴の知識が必要となります。 - 靴とのバランスを考えた保育方針
はだし保育を実施する場合でも、靴の教育時間を設けることで、靴への適応を促すことができます。例えば、屋外活動時には適切な靴を履かせる習慣をつけること、履き方を教育することで、今後の足の発達を手助けしてくれると考えます。
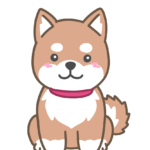
まず先生達(教育者)の足と靴の知識向上がもとめられます。
草履、下駄はどうなのか?
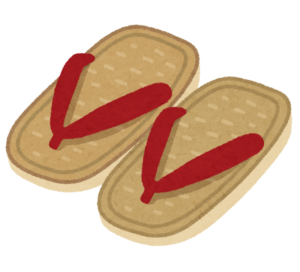
はだし保育の問題から脱線しますが、日本の昔ながらの履物、草履や下駄が、子どもの足にとってとても良い!という意見もちらほら耳に入ってきます。まず草履や下駄は、現代のアスファルトで舗装された地面に対しては、衝撃吸収の観点から機能不足と考えます。
草履はしっかり足趾(足の指)が使えるようになる!という意見もありますが、身体のバランスがある程度しっかりしていれば問題ないですが、まだ不安定なバランスの場合、余計な力が足趾にかかりすぎて、足指を掴むような癖が強くでてしまうこともあります。
また草履は、踵のサポートがないため、外反扁平足などのトラブルに対しては、バランスを悪化させる可能性があります。
個人的な意見になりますが、草履や下駄などを利用する場合、時間を限定したトレーニング要素として利用することは、大変プラスになると考えます。その時に、その子の個性に合うよう考慮してあげることが大変重要になります。
靴屋さん的見解というささいな話
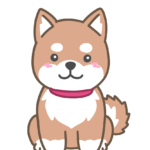
ここからは独自の見解になりますので、お気軽に読んでね。
はだし保育の現場での環境はそこまで詳しくないので、一概には言えませんが、親御さんからの話を聞くと、とりあえず「はだしが足にいいい!」という、なんとなくなイメージをお持ちの方も少なくありません。「牛乳は健康にいい!」みたいな…。牛乳も合う人と合わない人がいるように、はだしでの状態が、その子にとって、合う合わないは個人差が大きくかかわってくると感じています。
関節弛緩や外反足が強い子にとっては、はだしは不安定の極みであり、まわりの筋肉が発達し補っていればよいのですが、幼児にそれを求めることは不可能です。足元が不安定のまま生活していれば、姿勢の悪化はもちろんのこと、歯並びの悪化や、夜泣きなど、さまざまなトラブルにつながりかねません。
また、はだし保育を実践している園の子は、ふだんから靴下を履かないという状況もよく耳にします。靴を履くときも、はだしのようです。親御さんは「はだし保育を受けているから」という言い分をお聞きしますが、基本的に靴は、靴下を履いて履くように設計されています。靴を履くときは、吸湿性や足の保護、フィッティングの面で、靴下を履いたほうがメリットは大きいです。
はだしは実際、地面環境が優れていれば、足の発達において、非常に効果的と考えます。ただ現状はそのような環境は少なく、近くの公園に行っても、砂場が閉鎖されていたり、きれいに舗装された路面が多かったり…おとなでも裸足でいることがむずかしい環境になっています。
個人的な見解としては、どんな時もはだしが良いわけではないこと、個人差があること、を踏まえた上での、はだしの教育がすすみつつ、同時に靴の履き方等の靴の教育がすすむのが理想かな…と考えます。

というこで、今回ははだし保育の現状と問題点について記事にさせていただきました。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。
足と靴の知識を深めることは、日々の生活に直結する重要な要素です。皆さまに役立つ情報をお届けできるよう、今後も現場での経験と、専門的な知識をもとに記事を投稿してまいります。
引き続き、足と靴の健康を守るための情報を発信していきますので、ぜひチェックしてください。
good luck



